選択肢を失う恐怖 心を縛るお金の罠を解き明かすというテーマは、お金の問題を「ただ稼ぐ」「ただ貯める」だけの単純な話だと思いがちな方々にとって意外かもしれません。
僕たちは普段、豊かな暮らしを夢見ている一方で、お金が足りなくなると行動も思考も縮こまってしまう状況を、知らず知らずのうちに招いている場合があります(悲)
「お金がないと人生で何が起こるか」を考えることは、選択肢を奪う見えない敵と向き合うことでもあります。
子どものころから自然に身についてしまう“お金に対する思い込み”や、“貧すれば鈍する”という言葉に象徴される心理的な影響は想像以上に大きいもの。この記事では、心まで縛るお金の罠や、そこから生まれる負のループをひとつずつ解きほぐしながら、より豊かな未来の姿を検討していきましょう(というか意外と怖い話かもしれませんが、ちゃんと解決策も探っていきますのでご安心を笑)
では早速、この「心を縛るお金の罠」の扉を開いていきます。
なぜお金がないと選択肢を失うのか
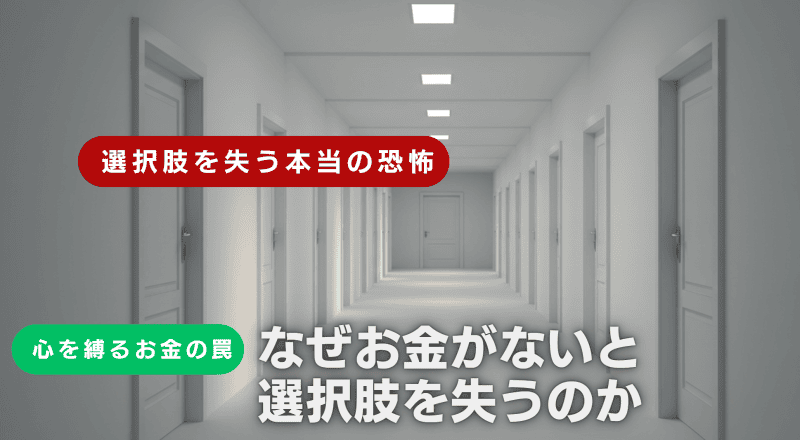
僕たちは日常の中で、「もしお金がたくさんあったら、好きなものを好きなだけ買えるのに…」という夢を描きがちです。
しかし実際に重要なのは「お金がなくなると、どうなるか」という点ではないでしょうか。
何かを買おうと思ったときに、低価格のものしか選べない状況や、そもそも何も買わない選択しか残されていない状況は、想像以上に大きなストレスをもたらします(悲)
これをただの「貧困」の話だと片付けてしまうと、本当にもったいないです。
なぜなら、そこまで極端な状況でなくても、お金がなくて選択肢が限定される瞬間は、誰にでも起こる可能性があるからです。
仕事での投資ができなかったり、自己啓発のためのセミナー参加を諦めたり、子どもに何か新しい経験をさせたかったのに費用面で断念したり。それらは日常のちょっとしたタイミングで、いつの間にか心の自由を奪ってしまいます。
僕は以前、ちょっと面白い話を聞きました。「買えるのに、わざと買わない」のと「お金がなくて買えない」のとでは、同じ結果でも精神的な感覚がまるで違うというのです。
これは機会費用や、ある種の自己決定感にも関わります。例えば、スーパーで安いイチゴしか買わなかったとしても、「あえて安いイチゴで十分だと思っている」のと「これしか買えなくて仕方がない」のでは、満足度に雲泥の差が生まれます(笑)
つまり、「選択の自由」というのがお金に深く関わってくる大きな要素です。
そして、それを妨げる目に見えない敵が存在します。
今から解説をしていきますが…
「お金がない状態とは、どんな風に人を追い詰めるのか」
「選択の幅が狭いことでどんな心理的負担が発生するのか」、さらに
「なぜそれが自己成長のチャンスも奪ってしまうのか」が、じわじわと見えてくるはずです。
選択する力の麻痺 ここに潜む見えない敵

お金がない状態だと、選択肢が激減してしまう。これは誰もが想像できるかもしれませんが、その裏にはいくつかの「見えない敵」が仕掛けを作っているとも言えます。例えば
複雑化という見えない敵 日々、情報量が莫大に増えていく社会では「本当はもっとお得な選択があるのでは?」と迷い続け、行動ができない方が増えています。お金の知識が乏しい人ほど「どれが正解か分からないから、とりあえず安いのを選んでおこう」という意思決定しかできなくなります。これは一見、堅実なように見えますが、実際には選択の幅を奪われているとも考えられます。
比較の罠という見えない敵 SNSや周囲の情報で「もっといい暮らしをしている人」を見て、嫉妬や不安を抱える。しかし、自分はそんなにお金がないから無理だ…と、一気に心が萎縮してしまう。気付けば、自分の可能性を限定する思考にどんどん囚われてしまいます。
過度な情報収集による見えない敵 「知識不足だから失敗するのでは」という恐怖から、学ぶことばかりを優先して実際の行動ができなくなる現象です。自己投資といっても、本来は投資を回収してこそ価値が生まれるはずが、「お金がないからもっと情報を集めよう」と堂々巡りになり、実際の行動が後回しになり続ける方も少なくありません。
これらの「見えない敵」は本人が意識していなくてもじわじわと忍び寄り、いつの間にか「やっぱりお金がないから仕方ない」という思考に追い込み、最終的に選択の幅をかなり狭めてしまうのです。
高まるストレスと『貧すれば鈍する』現象の正体
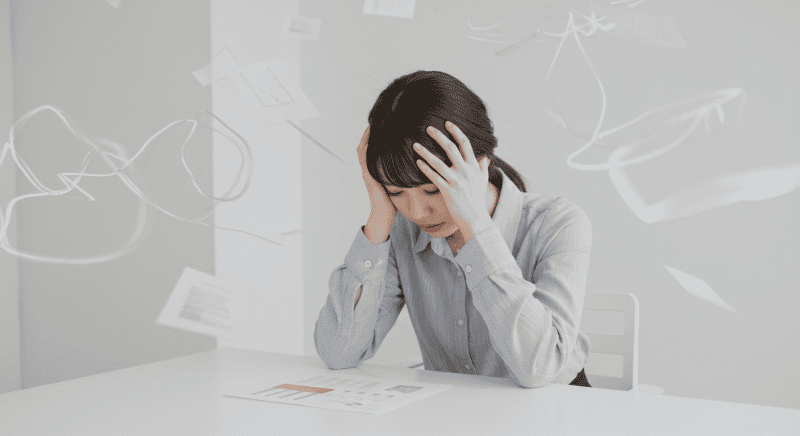
お金が足りない状況は、さまざまなストレスを引き起こします。
家賃が払えなければ住む場所が脅かされ、食費が足りなければ食事の質を落とさざるを得ない。
ほんの少しでも貯金があるときは何とか心の余裕を保てますが、ゼロやそれに近い状態に陥ると、不思議なほどに思考も行動も鈍くなってしまうのです。
昔から「貧すれば鈍する」ということわざがありますが、これは気のせいではありません。
たとえば、ハーバード大学のセンディル・ムッライナタン教授と、プリンストン大学のエルダー・シャフィール教授が行った実験を例に挙げてみましょう。
ショッピングモールにいた人たちに
「車の修理費が300ドルかかるが、保険で半分カバーされる。あなたなら修理に出すか、それとも騙し騙し乗り続けるか?」
という質問をし、続けて認知能力や実行力をチェックしたところ、経済的に余裕のある人と無い人とで大きな差は出なかったそうです。
ところが修理費が3000ドルになった途端、経済的に余裕のない層の認知能力と実行能力が著しく低下したという結果が出たのです。
要するに、
「お金がない」という状態によって、思考が狭まり、行動や判断に大きく影響が生じるということ。
これは「ストレスを抱えている」「不安に苛まれている」状態とほぼ同義であり、結果的に視野が狭くなってしまいます。
実は僕自身も、お金が少ない時期にあれこれ考えすぎて、最終的にうまく行動できなかった経験があります(悲)。
昔、ノウハウやツールの導入をどうしようか迷いつつ「費用がかかるなら今は保留…」と先延ばしにしてしまい、その間にチャンスを逃してしまったこともありました。
その時は頭のどこかで「また今度頑張ればいい」と思っていたのですが、実際はお金がない恐怖とストレスが、僕の行動の自由を奪っていたのだと思います。
意外と深刻 お金がない時こそ思考力が低下する理由
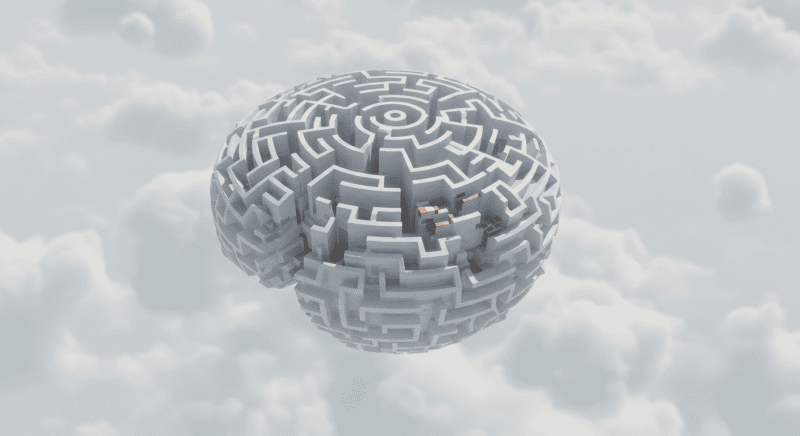
お金がないことでストレスを受ければ受けるほど、心理的には常に「どうやって生き残ろうか」という防衛モードに入ってしまいます。
すると、より大きな視点での「今後どんな人生を描くか」といった計画が二の次になり、「当面の問題をどう解決するか」だけに頭がいっぱいになります。
これが思考力の低下を招く一因です。
実際にインドの農民を対象に行われた調査で、サトウキビの収穫前と収穫後でお金の余裕が違うタイミングに同じテストを行った結果、収穫後のほうが思考力テストの点数が有意に高かったというデータがあります。
つまり、同じ人であっても「お金の余裕」があるときは冷静な判断ができ、「お金がない」ときは視野が狭くなる。
これだけ見ても、お金との距離感が心身に与える影響は決して無視できないと感じませんか。
もちろん「お金がすべて」ではないですが、あまりにお金がないと、最適な判断をすること自体が難しくなるのです。
そんなストレスフルな状態で無理に動いても、結果的に判断ミスを重ね、余計に損失を生むケースが多々あります。
これを「運がないから」と思い込む人もいますが、実は「お金がない状態による思考力低下」で判断が狂っていることも大いに考えられます。
子どもへの金融教育 使うか貯めるかは本来自由なはず

僕は金融教育ベンチャーの話を聞いたときに、強く共感した部分があります。
それは子どもが「自分で選ぶ力」を育めるように、お小遣いを与えるときにも「貯めるのも、使うのも、どちらが正解とかではない」という姿勢を示すという点です。
なぜなら、多くの大人が子どもにお金を渡す際「無駄遣いしてはダメだよ」と言いがちですが、それだけだと「貯める=善、使う=悪」という認識を植え付けてしまう恐れがあるからです。
本来であれば、子どもは「貯める」も「使う」も選択肢として持っていて、どちらを選ぶかは本人次第です。
そこで大切なのは「機会費用」や「選択には必ず何かを諦める側面がある」という現実を学ばせること。
これは大人になってからも重要な考え方で、「お金があるからこそ幅広い選択肢を検討できる」自立心につながります。
逆に、お金がないと「これしか買えない」とか「選ぶ余地がない」というふうに、自分の意思とは関係なく可能性を潰してしまいがちです。
子どもが将来、健全な金融リテラシーを身に着けるためにも、この段階で「自分の最適解を自分で見つける」経験をさせることが大切だと僕は考えています。
負のループに陥らないために 本当の稼ぐ意味を再確認する

お金がないことで選択肢を失い、ストレスを抱え、思考力も落ちる。そしてさらに稼ぐための投資すらできなくなる。
これはまさしく「負のループ」です。
二世代間で貧困が連鎖するケースもありますが、実は自分の人生の中でさえ、貧困状態に一度足を踏み入れると抜け出しにくくなることがあります。
とはいえ、必要以上にお金を稼ぐことを目的にすると、また別の方向で人を不幸にする可能性もあります。
ここで言いたいのは「ある程度のお金があれば、選択肢が増える」という事実を再認識することです。
例えば僕の場合、昔は「好きな資格を取るのにお金が必要だから」と、一時期バイトを掛け持ちしたことがありました。
その時は睡眠時間も削るほどきつかったですが、資格を取得したことでその後の収入が大きく改善し、結果的に時間の余裕ができました。
「まずは自己投資するためのお金を稼ぎ、そこから自分の可能性を広げる」というのは、大げさに聞こえるかもしれませんが、本当に大切なプロセスです。
もしも目の前に「これを学べば人生が変わるかもしれない」というチャンスがあっても、お金がないと飛び込めません。
ここが貧困の怖いところであり、見えない敵が根を張る領域です。
いつの間にか「自分はこれ以上成長できない」と思い込み、人生の選択肢を狭めてしまうことになります(というか悲しすぎますよね)
心を縛るお金の罠を断ち切るためにいま動く

ここまで見てきたように、「お金がないと選択肢を失う」という事実は、単なるイメージではなく現実です。
さらにお金の少なさが「思考力低下→ストレス増大→投資できない→可能性が広がらない→さらにお金が足りない」という悪循環を呼び込み、いつしか「自分には無理だから」と可能性を閉ざしてしまう。これは本当に恐ろしいことです。
だからこそ、必要以上に稼ぐのではなく「選択肢を失わないレベルの経済的なゆとり」はしっかり確保する姿勢が大切だと僕は思います。
貯金だけでなく、学びや仕事に対しても「今ここに投資すれば、自分の選択肢を大きく広げられるかもしれない」という視点を持つことが重要です。
そして子どもにも「貯めること」「使うこと」の両方に意味があると伝え、「自分で最適解を選べるようになること」が人生を豊かにすると教えてあげられたら最高です。
これは僕たち大人にとっても同じで、
「本当に価値あるものにお金を使う」
「無駄に浪費しない」
「でも必要な投資は躊躇なく行う」
というバランス感覚を磨いていきたいものですね。
もし今「お金が足りないからどうしようもない」と思い込んでいたら、まずは小さな一歩でいいので行動を始めてみてください。
副業を始める、スキルを身に着ける、短期バイトで一時的に資金を稼ぐなど、どんな方法でも構いません。
負のループから抜け出し、選択肢を広げるための行動です。今からでも決して遅くありません(というか、むしろ気づいたその瞬間が一番早いのです)
お金がない状況は決して恥ずかしいことではありません。
ただし、その状態が続くと「心までも縛る見えない敵」を呼び寄せる危険があるのです。
だからこそ、今日という日に改めて「心を縛るお金の罠」について理解を深め、必要最低限の経済的余裕を持つ大切さを認識しましょう^^
 やす
やす行動を起こせば、僕たちの未来はちゃんと変わっていくはずです(笑)
PS
実は前日に公開した、こちらの


特典の配信をスタートしましたが、いくつか質問とかも頂いているので、どんどんシェアしてコンテンツに反映していきたいな!と考えてます。
時間を削減しつつ、最高のパフォーマンスで副収入を構築していく。
「過去に色々挑戦したけど うまくいかない。」
「なんとなく学んでも、具体的なイメージが頭で湧かないので前に進めない」
などなど、本当にこういう人にこそ、大きな結果をだしてもらいたい・・
そのために出来る事を整理して、今回の森山哲夫さんのAPAというチート級のツールの特典で
ツールの機能を最大限に引き出す方法から、「そもそも どう展開していいの?」という疑問まで解決し全員が、「めちゃくちゃ良かった!」と思って貰えるような
「サポート」と「コンテンツ」これを提供できれば…と思ってます^^


では、今日はこの辺で。








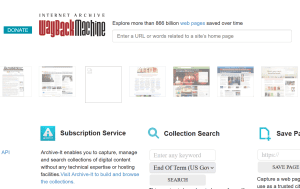
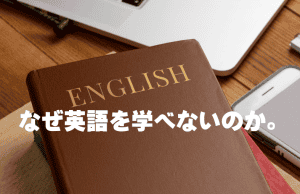
コメント